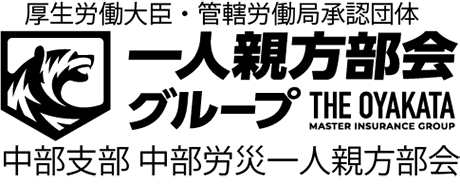建設業一人親方が納める個人事業税とは?まずは税金の種類を解説!建設業一人親方の個人事業税!有効な税金対策とは?
の4種類があります。節税するためにも、それぞれの計算方法や特徴などを知っておきましょう。 建設業の一人親方として納めるべき税金の代表が所得税です。毎年1月1日から12月31日までの事業所得に対してかかる税金です。所得には建設業の個人事業主の所得税を解説!
という10種類があり、建設業の一人親方の場合、該当するのは事業所得のみの場合がほとんどです。
ただし土地やマンションなどを所有していて、貸付をしている場合はその家賃収入は不動産所得を得ている場合がありますし、株のトレードやFXなどの投資がある場合は雑所得にあたります。
そしてこれら全てが所得税がかかります。
そして事業所得の申告方法は白色申告と青色申告があり、これによって控除額が変わってくるので、青色深刻は節税に有効な手段となります。
さらに所得とは粗利から経費を引いたもの。業務上で必要な出費は所得から引くことができるのですが、この経費に形状する項目を増やすだけでも節税ができます。
青色申告や経費でできる節税については、後ほど詳しく書きます。 住民税は所得税と同じく、毎年1月1日から12月31日までの所得に応じて計算される税金です。建設業の個人事業主の住民税を解説!
ただし所得税のように、確定申告の必要はありません。
所得税の確定申告で申告された所得に応じて、市区町村が税額を計算して請求をしてくれるからです。
その計算された納付書が4月に送られてくるので、それに沿って納めるだけです。
納付方法は6月末までに一括で納付するか、3ヶ月ごとに6月から2ヶ月ごとに4回にわけて納付する方法の2種類があります。
この住民税も所得に応じて、納付額は変わるので、控除を利用したり経費にできる支出を使えば節税ができます。 事業税も所得税と同じく、毎年1月1日から12月31日までの所得に応じて計算される税金です。建設業の個人事業主の事業税を解説!
ただし10種類ある所得の中でも、事業所得と不動産所得にのみかかります。
しかも一定以上の規模の事業または不動産の所得にかかるので控除額も大きく、所得のうち290万円以上の所得にかかってくるものになります。
所得が290万円以下の場合は事業所得がかからず、それ以上の所得がある場合でも290万円控除された金額に税金がかかります。
事業所得は業種によって税率が変わるのですが、建設業の事業所得の税率は5%ですので290万円を超えた所得の5%がかかるということです。
事業税=(所得-290万円)×0.05で計算ができます。
事業税も住民税と同じく申告の必要はなく、確定申告から市区町村が計算してくれます。
納付書が届くのでそれに沿って納付すればOK。
納付方法は8月末の一括か、8月と11月末の2回払いのどちらかを選択できます。
事業税も所得に応じた納付額ですので、控除や経費によって所得を抑えると、税額も抑えられます。 そして最後に消費税です。建設業の個人事業主の消費税を解説!
消費税はモノやサービスを購入した際にかかる税金で、購入金額に対して一律の税率がかかります。
ただし個人も事業者も購入者は販売者に対して消費税を支払い、一時的に販売者が預かり代わりに国に納付するシステムです。
ですから個人事業主も普段の請求から消費税を預かっていることになります。
ただし消費税はこれまでの3つ税金とは性質が異なり、事業主によって課税の対象にならない場合があります。
条件が合えば消費税は支払わなくていいのです。
その条件とは
全ての場合において計算するのは不可能なので、よくある家庭の1人親方を想定して書きます。
世帯主(40歳)・配偶者(35歳)・子供(10歳)・子供(9歳)の4人1世帯として考えました。
| 年収 | 手取り | 所得税 | 住民税 | 国民年金 | 国民健康保険 |
| 200万円 | 144.1万円 | 0.3万円 | 2万円 | 19.7万円 | 33.9万円 |
| 300万円 | 219.5万円 | 4.7万円 | 10.9万円 | 19.7万円 | 45.2万円 |
| 400万円 | 294.9万円 | 9.1万円 | 19.8万円 | 19.7万円 | 56.4万円 |
| 500万円 | 366.6万円 | 17.4万円 | 28.7万円 | 19.7万円 | 67.7万円 |
| 600万円 | 434.6万円 | 29.3万円 | 37.5万円 | 19.7万円 | 78.9万円 |
| 700万円 | 496.6万円 | 47.0万円 | 46.4万円 | 19.7万円 | 90.1万円 |
| 800万円 | 564.0万円 | 66.3万円 | 56.0万円 | 19.7万円 | 93.9万円 |
| 900万円 | 632.8万円 | 85.9万円 | 65.9万円 | 19.7万円 | 95.7万円 |
| 1000万円 | 697.2万円 | 110.1万円 | 76.9万円 | 19.7万円 | 96.0万円 |
建設業一人親方が確定申告時に知っておきたい節税のポイントとは!
- 基礎控除 38万円
- 配偶者控除 38万円
- 扶養控除 38万円
- 生命保険料控除 12万円(最大)
- 医療費控除
- 青色申告特別控除 (65万円)
建設業一人親方が確定申告をする際に経費算入できる勘定科目を解説!
- 接待交際費
- 地代家賃
- 水道光熱費
- 通信費
- 車両費
- 専従者給与
地代家賃
水道光熱費・通信費
車両費
専従者給与
こんなものまで経費計上できる
- カフェでの飲食代
- 慶弔費
- 祈祷代