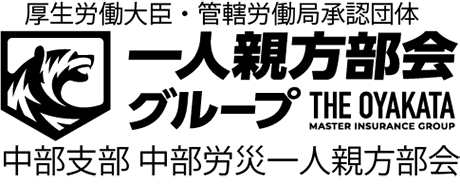税金は、できることならあまり払いたくないと感じる人も多いでしょう。
ですが、納めるべき税金を払わなければ、それは「脱税」となってしまいます。
特に、建築関係の1人親方として働いている方の中には、税金について正しく理解していないことで、知らず知らずのうちに脱税状態になってしまうリスクもあります。
そこで今回は、「どのようなケースが脱税にあたるのか」、そして「脱税が発覚するとどうなるのか」について、詳しく解説していきます。
確定申告をしてない
一人親方にとって最も多い脱税のケースが、「確定申告をしないこと」です。
確定申告とは、自分の年間の売上や経費をもとに、いくら税金を支払うべきかを自分で計算し、国に報告する手続きのこと。
言い換えれば、申告をしなければ税金も発生しない、そんな錯覚に陥ってしまうこともあるかもしれません。
実際、個人事業主として独立した後、確定申告を一度もしておらず、納税もしていないという人も珍しくありません。
「じゃあ確定申告しないほうが得じゃない?」と思ってしまうかもしれませんが、現実はそう甘くありません。
というのも、多くの個人事業主の売上は、すでに国に把握されているからです。
請求書を発行する際、「源泉徴収税」が引かれていた経験はありませんか?
これは、あなたが本来納めるべき税金の一部を、取引先が前もって天引きして国に納めている仕組みです。
表向きは「納税の手間を減らすため」の制度ですが、実際には脱税を防ぐための仕組みでもあります。
なぜなら、源泉徴収を通じて、取引先と支払額の情報がすでに国に報告されているからです。
つまり、あなたが確定申告をしなくても、「売上があったのに納税していない」ということはバレてしまうのです。
ただし、確定申告を怠ったからといって、すぐに罰金や追徴課税が科されるわけではありません。
中には、何年も放置している人もいるでしょう。
しかし、だからといって税金が免除されるわけではなく、未納の税金は年々積み重なっていきます。
そしてある日突然、税務署の担当者がやってきて、「これまでの税金をすべて支払ってください」と求められることも。
もし支払いを拒めば、銀行口座や取引先からの売上を差し押さえられる可能性すらあるのです。
つまり、確定申告をしなかったからといって逃げ切れることはなく、いつか必ずそのツケを払う日がやってきます。
確定申告をしないことで得られるメリットは、実は一つもありません。
単に、支払いを先延ばしにしているだけなのです。
確定申告をしたけど税金を払ってない
次に多い一人親方の脱税パターンは、「確定申告はしたものの、税金を支払わない」というケースです。
確定申告をすると、その場で税金を支払うこともできますし、後日コンビニで使える支払い用紙が届いたり、クレジットカードなどでの支払いも選べます。
申告を済ませた後は、基本的に「納税義務」が発生します。ただし、支払うタイミングは期限内であれば自由に選べるため、「ちょっと後で…」と放置してしまう人もいるかもしれません。
ですが、支払いをしなければならないという事実は変わりません。先ほどの「申告しない」場合と同様、逃げられるのはほんの一時だけ。
支払わないままでいると、税金の未納分はどんどん積み重なっていきます。
さらに、「重加算税」というペナルティもあります。これは、本来の税額に加えて10〜15%の追加課税が毎年上乗せされるものです。
つまり、支払いが遅れれば遅れるほど、納めるべき金額が増えていくということです。
確定申告をしたからといって安心してしまい、納税を後回しにするのはとても危険。
一時的にやり過ごすことはできても、最終的に税金から逃れることはできません。
そして、その納税額は時間が経てば経つほど膨れ上がっていくのです。
経費ではないものを計上する
そして、三つ目に多い脱税のリスクが高いケースが、「本来経費にならないものを経費として計上する」という行為です。
例えば、プライベートで使っている自動車の購入費を経費にしたり、事業とは関係のない外食の領収書を接待交際費として計上したりすることがあります。
交通費や外食費については、「どこまでが事業に関係していて、どこからが個人利用なのか」という線引きが非常に曖昧で、ケースによって判断が分かれるところです。
そのため、すべての外食が経費にできないわけではありませんし、見た目には事業に関係なさそうな自動車でも、使い方や状況次第では経費として認められることもあります。
しかし、それらが「事業に必要な支出である」という説明が論理的に成り立っていなければ、それを経費として申告することは、れっきとした脱税になってしまいます。
では、もし経費として認められない支出を申告してしまった場合、どうなるのでしょうか?
この場合、税務調査が入れば「追徴課税」の対象になります。
一方で、調査が入らなければそのまま通ってしまうケースもゼロではありません。
しかし、調査で発覚した場合には、本来納めるべき税金に加えて、加算税や延滞税などのペナルティが上乗せされます。
つまり、支払うタイミングを逃したことで、結果的に支払い金額が大きく膨れ上がることになるのです。
経費にならない可能性があるものについては、「これは経費に入れても大丈夫かな?」と迷った時点で、税務署に確認するか、信頼できる税理士に相談することが大切です。
安易な経費計上は、あとから大きな負担を招きかねません。
売上を隠す
最後に挙げられる脱税のケースは、「売上そのものを隠す」という行為です。
税金は「純利益」に対して課されます。
この純利益とは、「売上から経費を差し引いた金額」のことです。
そのため、納税額を抑えようとするなら、通常は経費をしっかり計上することで節税を目指すのが正しい方法です。
しかし、中には売上を少なく見せるという手段を選んでしまう人もいます。
たとえば、売上を申告しないために、銀行口座を使わず現金でのやり取りにしたり、別会社を作ってそちらに売上を分散させるといった方法があります。
こういったやり方で利益を減らし、結果として税金の支払いを大幅に減らすことも理論上は可能です。
ですが、これは明らかな脱税行為であり、法律違反です。
税務調査が入った場合には、隠していた売上分に対して「追徴課税」が課される可能性が高く、最終的には本来の納税額よりも多く支払わなければならなくなります。
事業で得た売上は、たとえ少額であっても正直にすべて計上することが鉄則です。
そうしておかないと、後から調査が入ったときに大きなトラブルになってしまいます。
意図的でなくても、うっかり売上の計上漏れがあると脱税と見なされることもありますので、十分に注意しましょう。
まとめ
本日は、一人親方にとって身近な「脱税」についてお話ししました。
目先の支払いを少しでも減らしたいという気持ちから、税金を少なく見せる方法は実にさまざまあります。
その中にはグレーゾーンとされる行為もありますが、中には明らかに「黒」と言える脱税も存在します。
だからこそ、脱税ではなく“正しい知識に基づいた節税”を行うことが重要です。
支払うべき税金はしっかりと納め、抑えられる部分は合法的に抑える。
それが一人親方として、長く安心して事業を続けていくための基本です。
無理にたくさん税金を払う必要はありませんが、適正な金額をきちんと納めておけば、後から余計なトラブルに巻き込まれることもありません。
ということで今回は、一人親方に起こりやすい脱税のパターンと、そのリスクについて解説させていただきました。
◆関連記事(国税庁HP引用):税務調査手続について
◆参考記事:一人親方が確定申告で無申告を続けた末路について解説!
投稿者プロフィール

-
【団体概要と運営方針】中部労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・岐阜労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【中部労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、中部労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
★一人親方部会グループ公式アプ→https://www.saitama631.com/app.html
★一人親方部会クラブオフ→https://www.saitama631.com/cluboff.html
■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』https://www.youtube.com/channel/UCZTlxZRxDDgren56lAn5boQ
最新の投稿
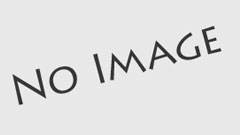 一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について
一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと
よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと 未分類2022年7月14日
未分類2022年7月14日 一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること
一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること