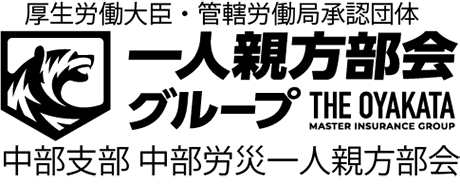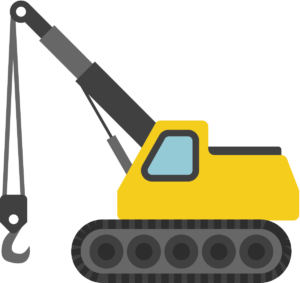
ICT建設機械とは、マシンコントロールシステムやマシンガイダンスシステムが組み込まれた建設機械のことを指します。
これらのシステムは、建機のオペレーションをある程度プログラムによって制御・補助できるようにするもので、自動制御や作業の精度向上に貢献します。
とはいえ、完全自動というわけではなく、特定の作業や動作範囲を制限・制御することで、安全性や効率を高める仕組みです。
たとえば「10メートル以上掘削してはいけない」という条件がある場合、機械が20メートルで自動的に動作を停止するように設定することができます。
また、機械の可動範囲を限定して事故を未然に防いだり、誤操作によるミスを減らすといった役割も果たします。
さらに、オペレーターの技術に頼らなくても作業の一定品質を保てる点も大きな特徴です。
未経験者でも作業をこなせるようになり、熟練者であればさらに短時間で高精度な施工を行うことが可能です。
つまり、ICT建設機械を導入することで、「誰でも・より簡単に・より早く」作業を行える現場環境を実現できるということです。
今回は、このICT建設機械の導入にあたってのポイント、そして導入によるメリット・デメリットについて、詳しく解説していきます。
ICT建設機械導入のポイント
ICT建設機械を導入するにあたって、いくつか押さえておくべき重要なポイントがあります。
まずはその中の一つ目、「予算と利益の見通しを正確に把握すること」についてご説明します。
ICT建設機械は、最新技術が搭載された非常に高価な設備です。
新たな建機の導入には一定のコストがかかることは皆さんご承知の通りですが、ICT機能付きとなると、さらに高額になります。
そして重要なのは、「導入したからといって必ずしも利益が出るとは限らない」という点です。
たとえば銀行融資を利用して導入する場合、返済額や金利も含めて、それに見合う利益が見込めなければ、経営にとっては逆にリスクとなります。
つまり、ICT建設機械を導入することで得られるメリット(利益)が、導入コストを上回るかどうかを事前にしっかりと見極める必要があるのです。
導入にかかる初期費用、予想される収益の増加、回収期間などをシミュレーションしながら、タイミングや資金計画を綿密に立てることが成功のカギとなります。
ICT建設機械を利用できる環境作りも必要
ICT建設機械を導入する際に、もう一つ重要なポイントとして押さえておきたいのが、「機械を活用できる環境が整っているかどうか」という点です。
ICT建設機械は、単に購入すればすぐに使えるというものではありません。
活用するためには、3D CADで作成された施工図や測量データなど、さまざまなデジタル情報が必要になります。
つまり、ICT建設機械の導入には、機械そのものに加えて、それを支えるための周辺設備や技術体制への投資も不可欠だということです。
たとえば、ICT建機専用の施工データを作成するためのオペレーターの確保、現場での基準点の設置、施工精度の確認体制などが必要になります。
これらの技術的な準備が整っていなければ、高価な機械を導入しても十分に活用することはできません。
とはいえ、こうした体制を構築できれば、人件費の削減や作業時間の短縮といった大きなメリットが得られるのもまた事実です。
ICT建設機械は、正しく運用すれば生産性を飛躍的に高めてくれる、非常に強力なツールだと言えるでしょう。
職人の理解を示す
最後のポイントは、職人さんの理解と協力を得ることです。
ICT建設機械は、職人の技術や経験に依存せずに一定の精度で作業を行うことを目的としたシステムです。
もちろん細かい部分ではオペレーターの技術差が影響することもありますが、基本的には個々の技能差によって作業結果が大きく変わらないよう設計されています。
つまり、長年培ってきた職人の技術や経験を一部否定する面もあるため、職人のプライドを傷つけてしまう可能性があるのです。
そのため、ICT建設機械を導入する際には、現場で作業する職人さんにあらかじめしっかりと理解を求めることが非常に重要です。
また、従来の技術が求められる難しい作業や特殊な施工には、相応の手当や報酬を用意し、職人さんの技能や努力に正当な評価を与える仕組みを整えることも効果的でしょう。
ICT建設機械のメリットは?
ここからは、ICT建設機械のメリットとデメリットについてご紹介していきます。
まずはメリットから見ていきましょう。
ICT建設機械の導入によるメリットは大きく3つあります。
そのうちの1つ目が、「作業時間の短縮」です。
作業時間が短くなると、次のような利点があります
-
人件費の削減ができる
-
工期(納期)を短縮できる
-
従業員が残業せずに利益を出せる
同じ作業内容であれば、仕事の価格は基本的に変わりません。
しかし、ICT建設機械を使うことで、より少ない人数・短い時間で作業を終えることができ、結果的に利益率を高めることが可能になります。
たとえば、通常であれば1週間かかる工事が、ICT建設機械を活用することで3日で終わるケースもあります。
そうなれば、同じ内容の仕事でも「より短い工期」で仕上げられる会社の方が、発注側に選ばれやすくなるのは明らかです。
納期に余裕が生まれれば、施工スケジュール全体の自由度も高くなります。
さらに、作業時間の短縮は従業員の働き方にも大きな影響を与えます。
建設業界では長時間労働が敬遠される一因となっており、それが人材不足や離職の原因にもなっています。
ICT建設機械を導入することで残業が減り、従業員が無理なく働ける環境が整えば、離職率を下げることにもつながります。
結果として、採用コストを抑えることができ、長く勤めてくれる人材を確保しやすくなるため、企業にとっても大きなメリットとなります。
このように、作業時間の短縮は「利益率の向上」「受注機会の増加」「人材の定着」といった多方面に好影響を与える、ICT建設機械の大きな利点と言えるでしょう。
安全性の向上とは
そして、ICT建設機械の最後の大きなメリットとして挙げられるのが、安全性の向上です。
ICT建機では、あらかじめ危険な動作や範囲を制限することができるため、事故のリスクを未然に防ぐことが可能です。
たとえば、機械のアームの可動域を制限したり、動作スピードに上限を設けたりすることで、オペレーターのミスによる接触事故や機械の暴走を防ぐことができます。
こうした「危険な状況をそもそも作らせない仕組み」が組み込まれていることは、現場における大きな安心材料となります。
建設現場では常に重大事故のリスクと隣り合わせです。
だからこそ、ICT建設機械の導入によって従業員の安全を守れることは、企業にとって非常に重要なメリットです。
安全性の向上は、労災リスクの低減や保険料の軽減にもつながり、長期的に見れば経営面でも大きな効果をもたらします。
参考記事:建設業界がIT化を進めるメリットとは
ICT建設機械のデメリットとは
オペレーターが育たなくなる可能性がある
まず1つ目のデメリットとして挙げられるのが、「オペレーターが育たなくなる可能性」です。
これはICT建設機械の導入にあたってよく指摘される懸念点の一つですが、実際にはそれほど深刻な問題とは言えないかもしれません。
なぜなら、そもそもICT建設機械の最大の特長は、「オペレーターの熟練技術に頼らなくても高精度な作業ができること」にあります。
つまり、経験や勘に依存せず、一定の品質で作業ができる環境を構築することが、ICT建機導入の目的でもあるのです。
これからの時代、すべてのオペレーターが従来のように長年の経験を積まなくても、ICT技術を活用した操作ができれば十分に現場で活躍できるようになります。
むしろ、ICT建機を使いこなすことに特化した新たな人材の育成が求められてくるでしょう。
ですから、確かに「従来型のオペレーターが育たなくなる」という側面はあるものの、それ自体が大きな問題とは限らないというのが現実的な見方ではないでしょうか。
導入が高額
2つ目のデメリットは、ICT建設機械の導入コストが非常に高額であるという点です。
この点は、間違いなく多くの企業にとってハードルとなる要素でしょう。
ただし、このデメリットも利益をしっかり生み出せるのであれば、大きな問題にはならないとも言えます。
たとえ初期投資が高額であっても、それによって作業効率が上がり、納期短縮や人件費の削減につながり、結果として利益が増えるのであれば、それは単なる支出ではなく「投資」と見るべきです。
つまり、設備導入コストというデメリットは確かに存在しますが、そのコストを上回るメリットを得られるかどうかがポイントなのです。
利益を生み出せる仕組みと運用体制が整っていれば、このデメリットは十分に相殺可能であり、むしろメリットに転じる可能性もあると言えるでしょう。
ットとも言い換えることもできるでしょう。
まとめ
現在、ICT建設機械の導入は各地で着実に進んでいます。
たとえ初期費用が高額であっても、適切な機械を導入し、正しく活用すれば、さらなる利益を生み出すことが可能です。
それだけでなく、他社との差別化を図るための強力な競争力にもなります。
一方で、こうした取り組みを怠り、競争力を持たないままの企業は、今後の人口減少やウッドショック・アイアンショックといった不安定な外部要因に直面した際、大きな打撃を受ける可能性が高いでしょう。
このような状況下では、経営判断のスピードが企業の生死を分ける要素になってきます。
ICT建設機械の導入を「検討中」のまま先送りにしてしまうと、その分だけ市場での立ち位置が弱まり、結果として事業の縮小や撤退につながりかねません。
ですから、現在ICT建設機械の導入を検討されている企業の方々は、早めの意思決定と行動が重要です。
競争力を高め、生き残るための選択として、今こそ本格的な導入を視野に入れるべきタイミングだと言えるでしょう。
投稿者プロフィール

-
【団体概要と運営方針】中部労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・岐阜労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【中部労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、中部労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
★一人親方部会グループ公式アプ→https://www.saitama631.com/app.html
★一人親方部会クラブオフ→https://www.saitama631.com/cluboff.html
■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』https://www.youtube.com/channel/UCZTlxZRxDDgren56lAn5boQ
最新の投稿
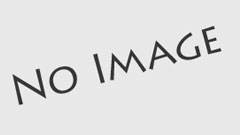 一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について
一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと
よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと 未分類2022年7月14日
未分類2022年7月14日 一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること
一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること