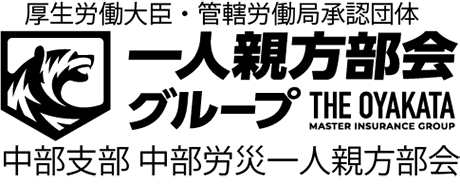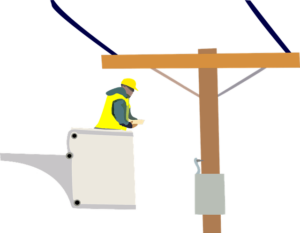消費税は本来、一時的にお客様から預かり、国に納めるための税金です。
しかし、売上が1,000万円以下の事業者や一人親方の場合、基本的には預かるだけで国に納める必要はありません。
ただし、一定の条件を満たすと、これまで売上に上乗せしていた消費税を、突然納税しなければならなくなる場合があります。
ここでは、一人親方さんと消費税の関係についてわかりやすく解説していきます。
一人親方さんにとって消費税は納めるべきもの
一般の人にとって消費税は、商品の定価に上乗せして支払う「邪魔なもの」に感じられるかもしれません。
しかし、一人親方として個人事業主になると、消費税は取引先から一時的に預かっているお金でもあります。
請求書に記載して受け取った10%の消費税は、自分の売上ではなく、お客様から預かったものです。
消費税は本来、消費した人の代わりに国に納めるためのものであり、たとえば飲食店で食事をした場合、消費税はそのお店に支払いますが、最終的には国に納められます。
つまり、私たちはお店に払っているのではなく、国に支払っているということです。
しかし、多くの一人親方さんにとって、消費税はつい自分の売上の一部のように扱われがちです。
ここからは、なぜ一人親方が消費税を支払わなくてもよい場合があるのかを解説していきます。
消費税を納めなくていい条件
消費税の納税義務がある事業者は課税事業者、納税義務がない事業者は非課税事業者と呼ばれます。
消費税を納めなくてもよい条件は、課税売上高が1,000万円以下であることです。
課税売上高とは、売上高から売上返品・値引き・割戻しなどを差し引いた金額のことを指します。
つまり、
-
売上高が1,000万円を超えなければ消費税の納税は不要
-
たとえ1,000万円を超えても、売上返品や値引き等を計上して課税売上高を1,000万円以下に抑えれば納税義務は発生しません
このため、課税売上高が1,000万円以下の一人親方や事業者は、消費税を請求して受け取っても、納める必要がないという、とても有利な立場にあるのです。
一人親方は消費税を請求してもいいのか
一人親方の多くは、課税売上高の条件から 消費税の納税義務がない場合 が多いでしょう。
非課税事業者の場合、「請求書に消費税を載せていいのか」と悩む方もいるかもしれませんが、心配は不要です。
消費税を納めるのはあくまで消費者の義務です。
非課税事業者であっても、消費税はお客様から一時的に預かっているだけであり、自分が納める必要はありません。
つまり、消費税を納める義務がなくても、請求して受け取ることは問題なく可能です。
一人親方の消費税はどうやって支払うのか
一人親方の場合、消費税の支払いについてあまり意識する必要はありません。
日常の買い物などでは、すでに商品に消費税が含まれており、特別に支払う手続きは必要ないからです。
しかし、課税事業者になった場合は注意が必要です。
この場合、取引先から預かった消費税を国に納める義務があります。
消費税の納税回数は、年間の預かり額に応じて決まります。
-
48万円以下:納税不要
-
48万円超~400万円以下:年1回
-
400万円超~4,800万円以下:年3回
-
4,800万円以上:年11回
ほとんどの一人親方は、年に1回の納税で済むことが多いでしょう。
逆に、年に何度も消費税を納めている事業者は、売上高がかなり高いと予想できます。
一人親方さんの消費税の計算は簡易課税で大丈夫です
一人親方の消費税は、売上高に応じて 簡易課税制度 を使って計算されることが多いです。
簡易課税とは、仕入れで支払った消費税を個別に計算せず、みなし仕入れ率 を使って消費税額を算出する方法です。
本来は、仕入れや売上ごとに消費税を計算して合算する必要がありますが、簡易課税を使えば経理や決算が簡単になります。
簡易課税制度を利用するには、課税売上高が5,000万円以下であることが条件です。
そのため、ほとんどの一人親方は簡易課税制度で消費税を計算すれば問題ありません。
課税売上高が1000万円を超えた場合の対策
もし課税売上高が1,000万円を超えると、原則として課税事業者と判定され、翌々年から消費税の納税義務が発生します。
ただし、これを回避する方法が一つあります。それは法人化(会社設立することです。
消費税の課税事業者判定は「2年前の売上高」を基準に行われます。そこで、課税事業者となった後に新たに法人を設立すれば、その法人には「2年前の売上高」が存在しないため、設立後しばらく(原則として2年間)は消費税の納税義務が発生しません。
つまり、個人事業主として課税事業者に該当した後に法人化すれば、法人としては一定期間(目安として2年)消費税を納めずに済む可能性があります。
この方法は合法の範囲で利用されている手法ですが、法人化には税制面以外にも社会保険や会計処理、設立費用などの影響があります。実行する前に、税理士など専門家へ相談してご自身の状況に合うか確認することをおすすめします。
インボイス制度について
ここで大きな問題となるのが、インボイス制度です。
この制度により、一人親方は課税事業者になるしか選択肢がない場合があります。
理由は、元請けが税金控除を受けるためには、適格事業者の発行する請求書が必要だからです。
適格事業者とは、8%と10%の消費税の内訳を明確にした請求書を発行できると国に認められた事業者のことです。
適格請求書でなければ、元請けは余分に消費税を支払うことになります。
適格事業者になるためには、消費税の課税事業者であることが条件です。
つまり、課税事業者にならなければ元請けにとって不利な下請けとなり、仕事が減る可能性があります。
一方、仕事を減らさないために課税事業者になると、自分も消費税を納める必要があるという、個人事業主にとっては二重の負担が発生する状況です。
まとめ
ここまで、一人親方と消費税の関係について解説してきました。
一人親方になると、これまで馴染みのあった消費税が少し複雑に感じられるかもしれません。
しかし、ポイントを押さえれば難しくありません。
-
課税売上高が1,000万円以下 → 非課税事業者
-
課税売上高が1,000万円を超える場合 → 法人化すれば2年間納税を免れることが可能
-
非課税事業者でも → 消費税を請求することは問題なし
この3点を理解しておけば、あとは確定申告の際に詳しく学べば十分対応できます。
また、インボイス制度が導入された際には、周囲の状況に応じて適格事業者になる必要が出てくる場合もあります。
投稿者プロフィール

-
【団体概要と運営方針】中部労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・岐阜労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【中部労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、中部労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
★一人親方部会グループ公式アプ→https://www.saitama631.com/app.html
★一人親方部会クラブオフ→https://www.saitama631.com/cluboff.html
■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』https://www.youtube.com/channel/UCZTlxZRxDDgren56lAn5boQ
最新の投稿
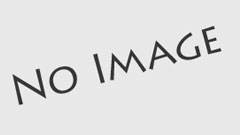 一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について
一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと
よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと 未分類2022年7月14日
未分類2022年7月14日 一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること
一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること