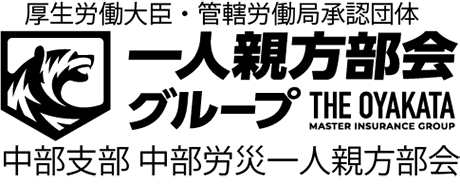一人親方様は必見です。
2022年からフルハーネス型安全帯が義務化されます。
それに伴い、建設現場において高所作業者は安全帯の買い替えと、講習を受ける必要が出てきました。
一人親方にとっても高所作業を行う場合には、受講の必要があります。
ここではフルハーネス型安全帯義務化の概要と講習。
そして補助金についても解説していきます。
フルハーネス型安全帯義務化の流れ
フルハーネス型安全帯は、厚生労働省の「第13次労働災害防止計画」で、建設業の労働災害の防止のため、着用の義務化も含まれており、建設業にとってはかなり問題視されております。
そしてその一部としてフルハーネス型安全帯が義務化される運びになりました。
ただ義務化と言っても、いきなりフルハーネスをどこの現場でも確実につけろよというわけではなく、段階的に適応されていくようです。
- 2018年3月 労働安全衛生法の施行令と規則などを改正するための政省令と告示の改正案を発表
- 2019年2月 新ルールによる法令・告示を施行。高さ6.75メートル以上でフルハーネス型の着用を例外
なく義務付ける(建設業では高さ5メートル以上)
- 2019年7月末 現行規格品の製造中止。
- 2022年1月 現行構造規格の安全帯の着用・販売を全面禁止。フルハーネス型安全帯 補助金
という流れ。
第13次労働災害防止計画の概要
第13次労働安全災害防止計画について、一部抜粋し少し触れておきます。
フルハーネス型安全帯の採用は、高所作業においての安全性を確保するために数年前から取り組みが行われているものです。
2022年には完全に施工されるのですが、第13次労働災害防止計画の一部です。
計画の目標
全体:死亡災害15%以上現象 死傷災害:5%以上現象
業種別:(建設業・製造業・林業 )死亡災害を15%以上減少、(陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店 )死傷災害を死傷年千人率で5%以上減少
8つの重点事項
- 死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
- 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進
- 就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進
- 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進
- 化学物質等による健康障害防止対策の推進
- 企業・業界単位での安全衛生の取組の強化
- 安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進
- 国民全体の安全・健康意識の高揚等
具体的な取り組み
(1)死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
- 建設業における墜落・転落災害等の防止
- 製造業における施設、設備、機械等に起因する災害等の防止
- 林業における伐木等作業の安全対策 等
(2)過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進
- 労働者の健康確保対策の強化
- 過重労働による健康障害防止対策の推進
- 職場におけるメンタルヘルス対策等の推進 等
(3)就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進
- 災害の件数が増加傾向にある又は減少がみられない業種等への対応
- 高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者及び障害者である労働
者の労働災害の防止 等
(4)疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進
- 企業における健康確保対策の推進、企業と医療機関の連携の促進
- 疾病を抱える労働者を支援する仕組みづくり 等
(5)化学物質等による健康障害防止対策の推進
- 化学物質による健康障害防止対策
- 石綿による健康障害防止対策
- 電離放射線による健康障害防止対策 等
(6)企業・業界単位での安全衛生の取組の強化
- 企業のマネジメントへの安全衛生の取込み
- 労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用
- 企業単位での安全衛生管理体制の推進 等
(7)安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進
- 安全衛生専門人材の育成
- 労働安全・労働衛生コンサルタント等の事業場外の専門人材の活用 等
(8)国民全体の安全・健康意識の高揚等
- 高校、大学等と連携した安全衛生教育の実施
- 科学的根拠、国際動向を踏まえた施策推進 等
という内容になっています。
この中の
1)死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
建設業における墜落・転落災害等の防止
なので、1番最初に取り上げられており、最重要課題だと言うことですね。
ですから現場によって多めにみてもらえるなどの、甘い対応ではなく、コンプライアンス厳守であり、大手ゼネコンの現場では必ず着用の義務が発生するでしょう。
フルハーネス型安全帯の着用ルール

フルハーネス型安全帯の着用ルールは以下の通り。
高さ6.75メートル以上でフルハーネス型の着用を例外なく義務付ける(建設業では高さ5メートル以上)要するに建設業では5mを超える高さである場合、確実に安全帯を付ける義務が発生するということになります。
例外はありません。
フルハーネス型安全帯新規格
フルハーネス型安全帯をすでに持っているという方も、過去の規格の安全帯は使えなくなってしまいますので買い替えが必要です。
現在すでに旧規格のものは製造が中止されていますが店舗で購入する際に、旧規格のものを間違えて購入してしまって、無駄な出費になる可能性もあります。
実は簡単に見分ける方法があって、それは「墜落制止用器具」と書かれているかどうかで判断できます。
旧規格のものには墜落制止用器具の記載はありませんので、この記載があるかどうかを確認して購入するようんしてください。
そして今回の法改正で安全帯という名称を使わなくなります。
普段のコミュニケーションでは安全帯と呼ぶことはあるかも知れませんが監査が入るような現場では正式名称で呼ぶ必要が出てくるでしょう。
法令用語としては「墜落制止用器具」と呼ばれるようになります。
これまで安全帯と言われていたもののうち一本つりの胴ベルト型、一本つりのハーネス型がこれに該当します。
U字つりの胴ベルト型安全帯は、墜落を制止する機能がないことから墜落制止用器具には認められません。
ネットでの販売には注意!
ネット上では信頼できるショップで買わなければ、新規格のものを注文したつもりが、旧規格のものが届いたということもあり得るはず。
さらにメルカリやヤフオクの安い商品はやめておいた方が無難です。
個人間の取引では、責任の所在を明らかにできないので、偽物をつかまされる可能性もあります。
胴ベルト型は必要なくなるのか
じゃあ胴ベルト型は必要なくなるのかというとそういうことではありません。
あくまでも5m以上の作業の場合に墜落制止用器具が必要というだけで決して、これまでん安全帯は5m以下の作業では引き続き使用が可能です。
フルハーネス特別教育
フルハーネス特別教育というものが存在します。
新ルール徹底のため、正しいルールを理解するための教育です。
フルハーネスと新規格への移行とともに、この教育の受講も義務化されています。
高所作業を行う作業員のうち、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業」に該当する作業員は全て受講する必要があります。
そしてフルハーネス型安全帯の使用のには猶予があります。
2022年までは5m以上でもフルハーネスをつける義務はありませんが、フルハーネスを使用する際は間違いなく受講を終えておく必要がありますので、順番にはご注意ください。
講義の内容は以下の通りです。
- 作業に関する知識
- 墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ。)に関する知識
- 労働災害の防止に関する知識
- 関係法令
などがありますが、試験はありません。
しかしデメリットは講義の合計時間が6時間で費用は1万円程度かかります。
フルハーネス型安全帯自体も1万円を超える金額になるので、合計で言えば2万円を超える金額になっています。
★受講する場所と日時については下記リンクよりご確認くださいませ。★
https://www.kensaibou.or.jp/seminar/index.html
フルハーネス型安全帯の補助金制度について

実はフルハーネス型安全チアからの買い替えに、50%の補助金が出ることになっています。
墜落制止用器具の規格(平成31年2月1日施行)に適合していない既存の安全帯から、構造規格を上回る「フルハーネス型安全帯」への買い替えにおいては上限10000円でかつ、購入金額の半額までを補助金で負担してくれるというもの。
具体的には、次に掲げる基準(追加安全措置)のうち2項目以上に適合するものが補助金の対象です。
- 背中X字腿V字型
- 2本ランヤード又は追加の補助ロープ(ランヤード+補助ロープ)
- ロック装置付き巻取器
- サスペンショントラウマ防止ストラップ
- ワンタッチバックル
- 反射板等
購入後に正しく申請を行えば、半額が返ってくるというもの。
もしくは販売店において代理で補助金の申請をしてくれるというものもあります。
基本的には代理での申請をしてくれる販売店で購入するのが、手続きが少なくてよさそうですね。
★詳細はhttps://www.kensaibou.or.jp/support/subsidy/full_harness_application.htmlでご確認くださいませ。★
まとめ
ここではフルハーネス型安全帯の法令と着用ルール、そして新規格と特別教育について触れました。
補助金も半額は出ますので、突然の仕事がやってきても対応できるようにしておきましょう。
そしてかなり面倒なフルハーネス型安全帯にはなりますが、基本的には作業者を守るためのものです。
しっかりと対策を行い怪我のないよに仕事してくださいますよう、よろしくお願いいたします。
関連記事:一人親方はキャリアアップシステムに登録しないと損をする可能性がある!?
投稿者プロフィール

-
【団体概要と運営方針】中部労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・岐阜労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【中部労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、中部労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
★一人親方部会グループ公式アプ→https://www.saitama631.com/app.html
★一人親方部会クラブオフ→https://www.saitama631.com/cluboff.html
■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』https://www.youtube.com/channel/UCZTlxZRxDDgren56lAn5boQ
最新の投稿
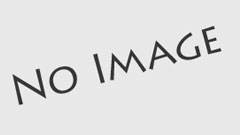 一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について
一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと
よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと 未分類2022年7月14日
未分類2022年7月14日 一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること
一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること