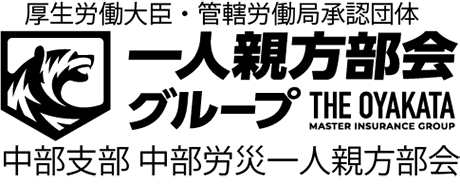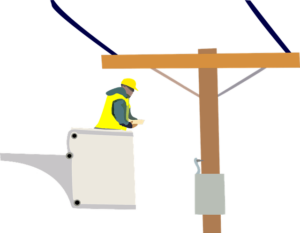左官工事は、壁や床を美しく仕上げるだけでなく、建物の耐久性や快適さを左右する重要な仕事です。
その高い技術を活かして一人親方として独立する人も多くいますが、自由な働き方と引き換えに「自分で守らなければならないリスク」が存在します。
ここでは、左官工事業の一人親方の皆さんが特に注意すべき「3つのリスク」を、違った視点から解説します。
① 天候・環境に左右されるリスク
左官工事は、気温や湿度、天候の影響を強く受けます。
モルタルや漆喰の乾燥が早すぎたり遅すぎたりすると、ひび割れや仕上がり不良が発生し、手直しやクレームにつながる可能性があります。
また、屋外作業が多いため雨天や冬季には工期が延び、収入の計画が崩れてしまうことも少なくありません。
一人親方にとって天候リスクは、直接「収入」と「信用」に響く大きな問題です。
② 技術トラブル・品質責任のリスク
左官工事は職人の技術力がそのまま仕上がりに反映されます。
もし施工不良が起きれば、やり直しのための材料費・人件費は自己負担になり、元請けや施主からの信用を失うリスクがあります。
さらに近年は、左官工事の工法や材料が多様化しており、新しい技術や仕上げ材への対応力が求められます。
知識不足や技術の更新を怠ることも、仕事を失う大きなリスクです。
③ 孤立・将来設計のリスク
一人親方の皆さんは基本的に「自分一人」で仕事を抱えるため、相談できる仲間が少なく、仕事の獲得や経営の悩みを抱え込みやすい傾向があります。
また、ケガや病気で働けなくなったときに収入が途絶えることを想定し、十分な貯蓄や保険を準備していないと、生活が立ち行かなくなる可能性があります。
さらに年金や老後の備えを怠ると、将来的に「引退後の生活資金が不足する」というリスクにも直結します。
まとめ
左官工事業の一人親方が避けるべきリスクは、
-
天候や環境に左右されるリスク
-
施工不良や技術トラブルによる品質リスク
-
孤立や将来設計の不足による生活リスク
現場での安全対策だけでなく、仕事の管理・人脈づくり・将来の備えまで意識することで、一人親方としての経営を安定させることができます。
投稿者プロフィール

-
【団体概要と運営方針】中部労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・岐阜労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【中部労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、中部労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
★一人親方部会グループ公式アプ→https://www.saitama631.com/app.html
★一人親方部会クラブオフ→https://www.saitama631.com/cluboff.html
■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』https://www.youtube.com/channel/UCZTlxZRxDDgren56lAn5boQ
最新の投稿
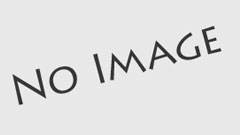 一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について
一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと
よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと 未分類2022年7月14日
未分類2022年7月14日 一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること
一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること