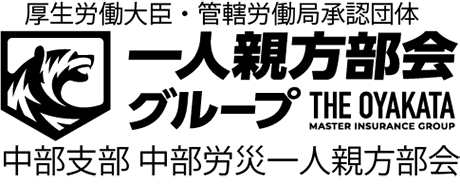開業届で登録する屋号は、名刺や請求書に使う長期的な「顔」です。一度広まると実質変更が難しいため、新しい屋号を決めるときは将来まで見通した慎重な判断が必要です。本稿では、屋号を付ける際の注意点と決定プロセスをわかりやすく説明します。
一人親方さんの屋号のポイント
ここからは屋号をつける時のポイントは7つ
- 仕事の内容がイメージできる名前にする
- 読みやすく、覚えやすい名前にする
- 同業者と被りにくい名前にする
- 将来の業務拡大に対応できる名前にする
- 法律・商標的に問題ないかチェック取引先に信頼される「真面目な印象」の名前にする
- ドメイン・SNSアカウントが取れるかも確認
屋号は一度決めると変更が実質難しい“看板”です。
「仕事の内容が伝わる → 覚えてもらえる → 信用される」
この流れを意識して付けると、長く使える屋号になります。
屋号はどこで使うのか

一人親方さんが屋号を使う場面は主に 請求書や領収書などの取引書類 です。
取引先へ請求書を発行するとき、領収書を受け取るとき、さらに振込先として銀行口座を開設する際にも屋号が使われます。
そのため、屋号をふざけた名前にしてしまうと、日常の取引で不都合が生じます。飲食店で領収書を受け取るときに毎回恥ずかしい思いをしたり、請求書を送る際に取引先から不信感を持たれたりと、仕事に影響が出る可能性があります。
屋号はビジネスの「顔」になるため、実務に支障が出ない名称を選ぶことが大切です。
屋号をつけるのは義務ではない
開業届には屋号を記入する欄がありますが、屋号の記載は義務ではありません。
最近では個人で働く人も増えており、屋号を持たずに 本名だけで仕事をしている一人親方の方も多くいます。
そのため、屋号は必ず付けなければならないものではありません。必要性を感じない場合は、本名だけで開業しても問題ありません。
禁止事項
① 「会社」「法人」などの紛らわしい名称は使用できない
一人親方(個人事業主)は法人ではありません。
にもかかわらず「会社」「法人」といった表現を使うと、法人と誤認させるおそれ があるため、屋号として使用することはできません。
② 商標登録された名称は使えない
商標登録されている言葉には、特許と同じく 独占的に使用できる権利 が存在します。
これを無断で屋号に使ってしまうと、最悪の場合「不正競争」とみなされ、損害賠償を請求される可能性 があります。
例として有名なのが「iPhone(アイフォーン)」の表記です。
私たちは普段「アイフォン」と発音しがちですが、「アイフォン」は日本ではすでに商標登録されており、Appleでも使用できません。
そのためCMでも公式サイトでも、必ず 「アイフォーン」 と表記されています。世界的企業でも避けている商標を、個人が侵してしまえば大きなリスクになります。
商標の確認方法
商標登録されているかどうかは、国が運営する 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) で検索できます。
税務署は屋号の商標まではチェックしてくれないため、事前に自分で必ず確認する必要があります。
屋号を付ける手順
ではいよいよ、屋号をつけていきます。
まず最初は候補をとにかくたくさん出しましょう。
もしシンプルな名前でよければ名字と専門をつなげた〇〇塗装とか〇〇電気みたいな名前がシンプルでいいでしょう。
ただ味気ないなと思う場合は色々な名前の候補を出してみてください。
こういったお仕事をするデザイナーやコピーライターは、名前の候補を100個ぐらいあげてみるそうです。
そしてその中で厳選していく。
ですから私達素人が考える際にも同じように、たくさんの候補をあげていきましょう。
この時のポイントは「これはさすがにないな」と思う候補であっても、書いて残していくこと。
勝手に判断して消去しないこと。
最初はまず数を出すことが大切です。
そうすることでどんどん候補が出てくるようになります。
候補を絞る
ある程度まで候補が出てきたら。候補を絞っていきます。
おそらく10個ぐらいまでは絞りやすいのではないでしょうか。
そこまで減ってきたら、特許情報プラットフォームで検索し商標登録されているか確認しましょう。
確実に屋号を決める前にやっておかないと、決めたあとに商標に引っかかってしまったら疲れてしまいますから。
Google検索してみる
ここまできたら次にGoogleで検索してみます。
そして同じ名前の業者がないか確認します。
なぜなら同じ地域で同じ名前の業者があると、そちらに仕事を取られてしまったり、グーグル検索でも上位を取られてしまったら、仕事が減ってしまう可能性すらあるからです。
大阪の業者を東京で気にする必要がありませんが、同じ地域の場合は違う名前に変更したほうが無難です。
決定する
最後は決めるしかありません。
友人に相談してみたり、自分でも一晩寝かせてから判断してみるのもいいでしょう。
今後10年間は名乗るものだと思って決めるようにしてください。
まとめ
屋号は必ず付けなければならないものでもありません。
しかし銀行で口座を分けたりする場合、仕事用の口座が屋号がついていると管理が楽になるでしょう。
最初に決めたら、あとでなかなか変更できませんのでじっくり考えるようにしてください。
なお屋号を決めるのは税務署で開業届を出すとき。
開業届けを出す前に必ず屋号を決めてから税務署に行くようにしましょう。
※所轄税務署を探す→国税庁より
参考記事→建設業一人親方が営業の名刺を作るときに気をつけるべきこととは?
投稿者プロフィール

-
【団体概要と運営方針】中部労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・岐阜労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【中部労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、中部労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
★一人親方部会グループ公式アプ→https://www.saitama631.com/app.html
★一人親方部会クラブオフ→https://www.saitama631.com/cluboff.html
■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』https://www.youtube.com/channel/UCZTlxZRxDDgren56lAn5boQ
最新の投稿
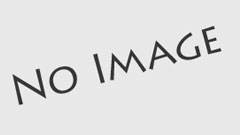 一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について
一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと
よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと 未分類2022年7月14日
未分類2022年7月14日 一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること
一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること