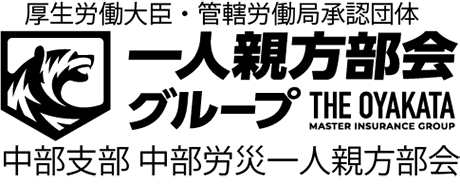今でも軽度の労災隠しは、建設現場で起きています。
小さな傷でも労災にしてしまうと手続きが大変なので仕方ないのですが、それでも隠し続けるといつかは大問題に繋がる可能性も。
今回は労災隠しの現状や、一人親方が労災を隠しているとどうなるかについて解説していきたいと思います。
一人親方が労災隠しをしているとどうなるのか
もし一人親方が労災隠しをするとどうなるのかというと、基本的には何も怒らない可能性が高いでしょう。
小さなけがをしたくらいで、現場に迷惑をかけたくないという思いから、多少のけがを目を閉じて無かったことにする。
時には骨折さえもなかったことにする可能性もあるでしょう。
それでもバレなければ問題ありません。何もなかったかのように時間は過ぎていくでしょう。
しかし何かのきっかけで労災隠しが表沙汰になった場合は、たくさんの場所に迷惑をかけます。
まず元請けには国から、指摘を受けるでしょう。
そして労災隠しをした元請けとして、世間からの風当たりが強くなります。
そして直接仕事をいただいた会社には元請けから仕事をいただけなくなる可能性があります。
もちろん労災隠しをした一人親方も噂になり仕事がもらえないようになるかもしれません。
つまり元請けや仕事をもらった会社、そして一人親方自身も誰も得はしません。
そして元請けの姿勢は、常にどんな細かな怪我でも労災として届けてもらうようにされているはずです。
ですからどんなに面倒でも、どんなに細かな怪我であっても必ず報告を怠らないようにしましょう。
労災隠しって一体どういうものなのか
労災隠しで多いのは、「治療費は会社で持つから健康保険で行ってきて。
道で転んだって言ってね」と会社から言われるパターンです。
仕事中の怪我はどんな理由があれど労災保険で治療を受けなければいけない法律になっています。
そしてアルバイトや契約社員だと、そもそも労災保険に加入していないと言われるケースもあります。
これは完全な嘘。
労災保険はアルバイトでも契約社員でも確実に加入しなければならず、正社員じゃないからといって労災を使えないことはありません。
そして「軽傷だから労災ではない」と言うのも間違い。どんなに小さな怪我でも労災です。
労災隠しはなぜ起きるのか
労災隠しの原因は1つではありません。
- 一人親方の労災未加入問題
- 労災を使うと保険料が上がる
- 元請会社の風評被害懸念
- 労基の監査を懸念(現場稼働停止リスク)
などがあって、ほとんどの場合は元請けの指示ではなく、個人的に現場に気を使って「迷惑をかけたくない」という気持ちでやることが多いでしょう。
昔は元請の圧力などもあったと思いますが、現在では元請に知られたくないという下請会社としての労災隠しがほとんどです。
一人親方の労災未加入問題
労災隠しの原因は一人親方の労災未加入問題があります。
現在大手の建設現場では一人親方であっても、労災の加入を求められます。
加入していなければ現場に入れないケースもある。ですから一人親方は労災保険に特別加入しています。
しかしその書類や監視を掻い潜って、働く一人親方さんっていらっしゃますよね。
現場の業務中での事故の怪我の治療は労災保険で治療しなければならないのですが、監視を掻い潜った一人親方さんは労災保険に加入していないため。
労災であることを隠し、国民健康保険を利用して治療を受けるためにプライベートでの怪我として治療を受けます。
そして現場の責任者に労災未加入が見つかってしまえば、その後現場に入れなくなる可能性もあり、それは一人親方にとって死活問題です。
その結果、現場には事故を伝えずに病院に行くことになります。
このため労災未加入の一人親方は労災隠しの原因になります。
労災を使うと保険料が上がる
2つ目の労災隠しの原因は、労災を使うと保険料が上がることです。
自動車保険を思い出していただければ想像しやすいと思うのですが、労災保険は保険を使うと次年度の保険料があがります。
保険を使えば最大で30%ほど保険料が上がることになり、会社の財政に負担をかける可能性があります。
建設業では普段から事故や怪我の多い業種であり労災保険を頻繁に使います。
ですから今年は労災保険をたくさん使っているという会社では、保険料が上げないために労災を隠し、健康保険の利用を従業員に強いる会社が存在します。
元請会社の風評被害懸念
大手建設会社の世間体や風評被害を防ぐために、労災隠しが行われる場合もあります。
建設会社では元請会社が労災事故の責任を持つことになっています。
ですから事故が多い現場ばかりの元請けではなかなか仕事が受けにくくなる恐れがあるというわけですね。
労災が増えることで事故が多い会社だと思われたくない。
その結果、元請からの命令により下請や孫請会社で労災隠しになってしまうのです。
下請はこれからも仕事をもらうためには、仕方がなく従業員に労災隠しを強要することになるのです。
労基の監査を懸念(現場稼働停止リスク)
最後の労災隠しの原因は、労基の監査です。
大きな長期にわたる現場では事故が多かったり重大事故が発生すると、労働基準監督署(労基)の監査が入ります。
そうなれば現場いは数日間泊まります。
建設現場ではタイトなスケジュールで動いていて、資材の搬入や人の配置もスケジュールを組んで動かします。
1日現場が止まれば、全ての資材や人を後ろにずらさなければなりません。
各協力会社もこの現場だけで動いていればいいのですが、他の現場にも入っていることも多く簡単にスケジュールを動かすことはできません。
つまり現場をできるだけ止めたくはないわけですね。ですから事故が大きければ大きいほど、元請は労災を隠したくなるものです。
労災隠しが発覚した場合の罰則とは?
労災事故は全て報告する義務があります。
労働安全衛生規則の第97条に労働者死傷病報告について書かれています。
(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における
負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書
を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一
月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事
実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。
労働者死傷病報告とは、労災の報告のことです。
このように事業者には労働中や就業中に怪我などの事故が起きた場合に、労働基準監督署に報告する義務があります。
そして労働安全衛生法の第100条でもこの報告に対し、労働基準監督署長が強制できる旨が書いてあります。法律上でも労災隠しは違法だということですね。
罰則は同120条において、書かれており、違反した場合は50万円以下の罰金が課せられます。
罰則については思ったより軽い罰則であったのではないでしょうか?会社として50万円の罰金というのはそこまで重いものではないかもしれません。
ただし労災隠しは社会問題であり、50万円支払うだけで済むものではありません。
建設業界で労災隠しが表沙汰になればこれからの受注に影響が出るでしょう。罰則より社会的な責任のほうが重くのしかかるでしょう。
一人親方と元請の責任の所在は?
では実際に労災が起きた時、その労災の責任を負うのは、元請と一人親方のどちらにあるのかという問題です。
原則として労災の責任は元請が持ちます。
これには元請企業と下請企業そして一人親方には雇用関係はないですが、実質的な使用関係があります。
元請企業が使用者で一人親方が労働者という関係が成り立っています。
(それを理由に一人親方は労災への特別加入が許可されています)
そして労働契約法第5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をするものとする。」となっており、これを安全配慮義務と言います。
簡単に言い換えると、元請企業は一人親方が安全に働ける環境を作る義務があるということ。ですから怪我をした場合は元請が責任を持ちなさい。と国が言っています。
労災の責任も労災の加入責任も元請にあるということですね。
ただしこれは原則であり、裁判の判例では元請だけでなく、一次請負などの実質の使用者への責任も認めています。
労災隠しの予防策として一人親方の労災保険へ加入しましょう
責任は元請にありますが、その代わり労災事故が起きた場合に一人親方が労災に入っていなければ、次から仕事を受注できなくなります。
なぜなら労災事故が起きた時、怪我をした本人が責任を負うのではなく、国はその責任を元請に求めます。
つまり元請けに対し重大な迷惑をかけてしまうということ。ですから必ず一人親方は労災保険に加入しましょう。
関連記事:一人親方労災保険の選び方
その他にも一人親方は労災保険に入るメリットがあって、怪我をした場合の治療費などは全て保険の負担になる(1円も支払わなくていい)。
そして医師の判断のでの休業の場合は休業補償も出ます。つまり一人親方が怪我をした際の、保険としてとても優秀なんです。
このように一人親方は労災保険に加入することがとても大切です。
建設業一人親方の労災隠しとは?まとめ
建設業一人親方にとって労災隠しは自分だけの問題ではありません。
元請との関係性を壊す恐れのあるものです。元請は国から現場に入る全員に対し労災保険に加入させることを義務付けており、労災事故において責任を取るのは元請会社です。
ですから元請会社に迷惑をかけないためにも、一人親方の労災加入は必須です。
実際に怪我をした際の、保証についてもかなり手厚いので、一人親方はこれを機会に労災保険の加入を検討するようにしてください。
投稿者プロフィール

-
【団体概要と運営方針】中部労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・岐阜労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【中部労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、中部労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
★一人親方部会グループ公式アプ→https://www.saitama631.com/app.html
★一人親方部会クラブオフ→https://www.saitama631.com/cluboff.html
■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』https://www.youtube.com/channel/UCZTlxZRxDDgren56lAn5boQ
最新の投稿
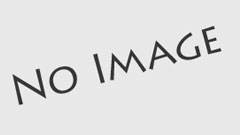 一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について
一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと
よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと 未分類2022年7月14日
未分類2022年7月14日 一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること
一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること