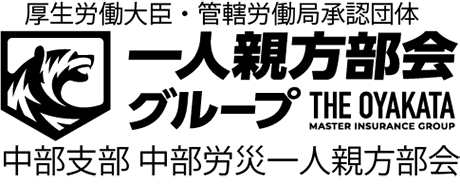一人親方になれば所得税はどうやって支払うのでしょうか?
会社員のころ所得税は給料から天引きされていましたが、一人親方になれば所得税はどうやって支払うのでしょうか?
申告しなければバレないんじゃないかと思っていると痛い目に遭います。
確定申告をして自分で所得額を申請し、その申請によって所得税が決まり、前年度の1年分の所得税を支払うようにしましょう。
そして無駄な税金を支払わなくてもいいように、経費をしっかりと計上することを忘れないでください。
一人親方は所得税申告をして、所得によって金額が決まる
所得税は収入に応じて支払う国税です。
一人親方になって支払う税金は3つあります。
- 所得税
- 個人事業税
- 住民税
このうち所得税のお話です。
一人親方になる以前でも、給料から天引きされていた税金ありますよね?それが所得税と住民税です。
この中でも所得税は年間の所得から計算をします。
確定申告を行い、それにともなって税額が決定するので支払うということになります。
確定申告をしなければ納税しなくていいの?
確定申告は自分で「所得がこれだけあるので、納税額は〇〇円です」と申告をするものです。
では申告しなければ、納税しなくてもいいんじゃない?バレないんじゃない?と思うかもしれません。
しかしそううまくはいかないのです。実は源泉徴収税というものがあり、一時的にあなたが納税すべき税金を他の企業が預かって代わりに支払うという仕組み。この源泉徴収税によってあなたが所得を得ていることは税務署に把握されています。
ですからもし確定申告をしなくても所得税は発生しており、期日までに支払わないor申告しない場合は、追徴課税といって通常より多い金額の納税が課されます。
さらに申告をしなかったり過少申告した場合は、所得税法により罰則が決まっており、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金になる可能性があります。
必ず確定申告を行い納税するようにしてください。
所得税を納めるための確定申告の方法

確定申告は前年度1月から12月までの所得の合計を申告します。
決められたフォーマットがあり、決められた期日までに行わなければなりません。
まず確定申告は2月15日から3月15日の間で行う必要があります。そしてそのフォーマットには
- 白色申告
- 青色申告
という2種類の方法があります。
※一人親方の青色申告についてはこちら
白色申告と青色申告
一人親方として確定申告する際には、青色申告をおすすめします。
このあと紹介する所得税を抑える方法にも書きますが、青色申告は税法上のメリットが大きく節税しやすいからです。
青色申告には帳簿付けなどが面倒な部分でもありますが、今は会計ソフトやアプリが発達していて、そのアプリ通りに入力していけば確定申告の必要書類が出来上がるので、昔に比べ確定申告がかなり楽になりました。
青色申告の場合は明確に節税が可能になります。税理士に依頼するのも1つの方法です。
所得税を抑える方法
ここで所得税を抑える方法についてお教えしましょう。
一人親方のほとんどが税金がもう少し安くならないかな?と考えていると思います。その方法はあります。
所得税を減らすには、
- 控除
- 経費計上
をうまくすると良いでしょう。
もちろん脱税はいけません。しかし知識を持っておけば、本当は支払わなくていい税金も支払わずに済みます。
控除を活用する
まず節税として活用できるのが、控除です。
控除とは課税前に所得から、引ける金額のことです。
要するに控除を利用すればするほど、税金は抑えられるということ。一般的に一人親方が受けられる控除は
- 基礎控除 38万円
- 青色申告特別控除 (65万円)
- 青色事業専従者給与
- 配偶者控除 38万円
- 扶養控除 38万円
- 生命保険料控除 12万円(最大)
- 医療費控除
- 確定拠出年金
これだけあります。
この他にもありますが、代表的なものをまとめました。基礎控除は38万円。国民全員が受け取れる控除です。そして青色申告特別控除と青色事業専従者給与がポイントです。
青色申告特別控除は青色申告の場合にのみ使える控除で、65万円もの控除が受けられます。
さらに家族などに仕事を手伝ってもらい、給料を出すことで、その金額は青色事業者専従者給与になり経費として計算できます。簡単に言えば、家族に給与を出すだけですべて課税前所得から引かれて、経費にできるということ。建設業であれば、10万円/月程度は可能ですので、年間で120万円。
もし白色申告にしていれば、専従者給与ではなく配偶者控除になり38万円の控除になるので、青色申告は白色申告に比べて150万円程度も課税前所得が変わります。青色申告にするだけで65万円+120万円=185万円もの控除が受けられる計算になるのです。節税したいなら青色申告ははずせません。
この他にも、扶養すべき家族がいれば扶養控除、生命保険に入っていれば生命保険控除、年間の医療費が高ければ医療費控除が受けられます。
節税としての確定拠出年金
そして個人事業主として活用すべきなのが、確定拠出年金です。
個人事業主は厚生年金がなく、定年後は国民年金のみで生活する必要があります。ただしその金額は約7万円/月。7万円でどうやって生活するのでしょうか。
税金対策として、将来への蓄えとして活用するのが確定拠出年金です。
確定拠出年金は毎月の支払いをすることで、定年後に受け取れる積立金を作るもの。
確定拠出年金と貯金がどう違うのかといえば、積み立てはすべて経費で行えるというところ。
貯金は税金を支払って、残ったお金から貯めますが、確定拠出年金で積み立てるお金の一部は税金で支払う予定だったお金。
税金の分だけ多く積み立てられるので、目に見える節税ではありませんが、生涯で考えるとかなり多くの節税を行える計算です。
経費計上を活用する
節税の方法の2つ目が経費計上です。
一人親方が経費計上できるものには以下のようなものがあります。
- 自動車購入費と維持費
- 移動費
- 事務所費
- 接待費
- 組合費
- 工具などを購入費
などがあげられます。
実際の経費科目とは違いますが、わかりやすく説明するためなのでご理解ください。
仕事の移動などに利用する自動車の購入や維持費そしてガソリンや高速料金に関しては、すべて経費に計上できます。ただし購入費用は減価償却しなければいけないので、6年間に分割して経費計上しなければなりません。
事務所を自宅とは別で借りている場合はもちろん経費ですが、自宅兼事務所の場合でも使用面積で按分して経費計上しましょう。
仕事の仲間との打ち合わせや食事会などの費用は接待費として計上できます。
この他にも組合費、工具の購入費用や材料費など、仕事にまつわる費用は経費として計算ができます。計上しなければ、その分税金のもとになる課税前所得に計算されてしまいます。
所得税を抑えるには、経費計上をうまく活用するようにしてください。
消費税について
所得税の他にも気をつけるべき税金があります。それは消費税です。
ちなみに消費税を請求書に上乗せをしているのは自分で受け取ってはいけません。預かっているだけのお金なので後ほど国に納税する必要があるんです。
このからは、一人親方の消費税の取り扱い方について書いていきます。
一人親方にとって消費税は納めるべきもの
一般的な消費者にとって、消費税は支払うものでしかありません。
しかし一人親方として個人事業主になった今、消費税は取引先から預かっているものでもあります。消費税は請求して受け取っていると思いますが、実は自分の売り上げではありません。
お客さんから計算した消費税率分を一時的に預かっているだけであり、消費した人の代わりに国に納める税金です。
例えば飲食店でご飯を食べた場合、本来消費税は国に支払うものですが、お店に対して支払いますよね。
これはその飲食店があなたが支払うべき消費税を一旦預かっているだけで、まとめてその飲食店があなたの代わりに国に消費税を納めてくれると言う仕組み。
ですから一人親方も売り上げが上がった場合に消費税を徴収して、お客さんの代わりに国に納税をする必要があります。
消費税を納めなくていい条件
消費税を納めるのは事業者の義務ですが、消費税の納税義務のない事業者も存在します。
消費税の納税義務がある事業者のことを課税事業者と呼びます。反対に消費税の納税義務がない事業者のことを非課税事業者と呼びます。できれば消費税は収めたくありませんよね?
消費税を納めなくても良い条件をここでお伝えします。それは課税売上高が1千万円を超えないようにすればいい。
課税売上高とは売上高から経費を引いた、所得税がかかってくる売上高のこと。そもそも売上高が1千万円を超えなければ、課税する必要はありませんし、もし1千万円を超えたとしても経費を計上して、課税売上高を1千万円以下に収めれば、消費税の納税の義務はございません。
一人親方で、現実的には売り上げ1千万円を超える人はそこまで多くないように思えます。
所得税は確定申告で金額が決まる
一人親方になると1年に1回、2月15日から3月15日の間に確定申告を行う必要があります。
その確定申告によって所得税が決まり支払いをします。
一人親方は所得税を支払えるように、1年間準備をしておかなければいけません。
そして納税をしたくない気持ちはとてもわかりますが、確定申告をしなくても一人親方の収入は税務署に筒抜けです。
納税から逃れることはできませんので、税金の知識をしっかりとつけて、払わなくていい税金は徹底的に払わないようにしましょう。
苦手なのであれば税理士さんに依頼するという方法もあります。
自分が住んでいる所在地の税務署検索はこちら
※国税庁ホームページ引用
投稿者プロフィール

-
【団体概要と運営方針】中部労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・岐阜労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【中部労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、中部労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
★一人親方部会グループ公式アプ→https://www.saitama631.com/app.html
★一人親方部会クラブオフ→https://www.saitama631.com/cluboff.html
■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』https://www.youtube.com/channel/UCZTlxZRxDDgren56lAn5boQ
最新の投稿
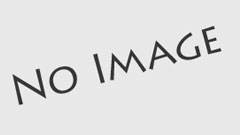 一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について
一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと
よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと 未分類2022年7月14日
未分類2022年7月14日 一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること
一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること