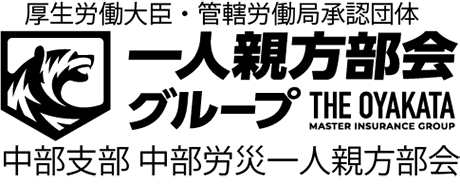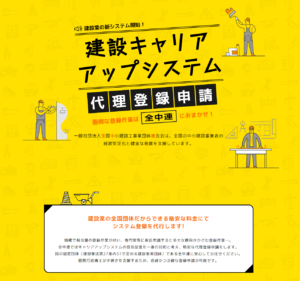会社員であれば退職をしたときに自動的にもらえる退職金ですが、一人親方は自分で準備する必要があります。
しかも退職金を準備するのであれば、個人事業主としてではなく法人として準備したほうが税金を抑える効果もあります。
今日はこの一人親方の退職金の作り方についてお話ししていきましょう。
一人親方の退職金の作り方
まず具体的に、一人親方の退職金の作り方について触れていきましょう。
- 貯蓄をする
- 小規模企業共済
- 建設業界退職金共済制度
- 法人化と生命保険
という方法があります。
貯蓄をする
まず1番簡単な方法が、貯蓄をする方法です。
厳密に言えば退職金ではありません。ただ単に老後に必要なお金を持っておきましょうという話です。
しかしこの方法は全くオススメできません。なぜなら税制上のメリットがないからです。収入の中から貯蓄をするのであれば、所得には所得税という税金がかかり、税金を支払う必要があります。
この方法では全く節税ができておらず、個人事業主のメリットをいかせていません。
貯金によって老後の蓄えを行う方法は、一人親方にとって最も損をする年金の作り方です。
小規模企業共済
小規模企業共済は国の機関である中小機構が運営する退職金制度です。
この小規模企業共済の掛け金は全額所得控除できるので、節税効果が高いのが特徴です。
言い換えると節税できるってこと。
貯金だと税金を払わないといけないけれど、小規模企業共済は税金を支払わなくていいのでお得です。
小規模企業を利用すれば、経営者や役員、個人事業主は退職金を作れます。
掛け金は1000円~70000円/月で、自由に選べます。
そして収入の増減に合わせて掛け金を増額もしくは減額することも可能。これにより収入を安定させるのが難しい一人親方でも、安心して積み立てられます。
積み立て額は中小機構の公式サイトでシミュレーションができるのですが、
- 掛け金30000円/月
- 20年間積み立て
で計算してみると、1784万円の退職金を作れるのです。そして年間で15万円以上も税金を抑えられる試算となりました。
つまり足りない2000万円問題を埋めることが可能。
このように小規模企業共済を利用し積み立てていけば、税金をできるだけ支払わずに退職金を作れます。
建退共制度
建設業界専門の建設業界退職金共済制度という退職金もあります。
これは一般的には建設業界の会社員の退職金を積み立てるための制度です。
一人親方を数人あつめて、任意組合を結成しすれば共済手帳の交付を受けられることになっています。
つまり本当は会社員のための制度ですが、一人親方も特例で加入できるってこと。しかも年利は2.7%ととても優秀な退職金共済。
ただし弱点は金額。
掛け金の上限が低く、310円/日しか掛け金にできません。
ですから40年加入していたと計算しても、最大で700万円程度しか退職金を積み立てられないところには注意が必要です。
法人化して生命保険を利用する
最後に法人化して生命保険を利用して退職金を作る方法についてお伝えしておきます。
一人親方は個人事業主の方も多いと思いますが、退職金を作るのなら法人化をオススメします。なぜなら退職金を作る場合は法人のメリットが大きいからです。
- 生命保険の掛け金を経費に計上できる
- 退職金も税制が優遇されている
というメリットがあります。
生命保険の掛け金を経費に計上できる
退職金のために法人化する最大の理由は、生命保険の掛け金を経費に計上できる点です。言い換えるとかなり節税できるということです。
法人では社長や代表の生命保険に加入できるのですが、返戻金がある保険に加入すれば退職金として積み立てができます。
100歳定期などの長期契約を組めば、加入から数年で返戻率は90%近くになりますし、若い時(20代)から入ればわりと早いタイミングで100%を超えます。
そして死亡保険金を5000万円や1億円などの高額な保険に加入すれば、多くの保険料を節税しながら支払える。
要するに生命保険に加入しているけど、解約をすればその保険料がほとんど返ってくるということ。
しかも経費計上できるので、毎年税金を支払う代わりに退職金を積み立てていける。
法人の経費であれば、課税前なので利益さえ出ていれば多くの保険料を支払える。というメリットがあります。
そして退職金を受け取る年齢になれば、保険を解約し返戻金を受け取って、退職金に当てればいいのです。
退職金の受け取りは課税が少ない
ここで問題があります。
法人は社長とは別人格。ですから退職金の受け取りは所得となり、その分所得税がかかってしまいます。
ただしここでも法人にはメリットがあります。それは退職金控除が受けられるということ。冒頭でも書きましたが
- 勤続年数が20年未満の場合は勤続年数×40万円
- 勤続年数が20年以上の場合は、800万円+70万円(勤続年数-20)
これだけの控除が受けられます。
25歳から60歳まで働いて、勤続35年だとしましょう。勤続35年の場合は、800+70×15年=1850万円の控除が受けられる。
言い換えれば1850万円までの退職金は非課税だということです。奇しくも2000万円問題が解決できそうな金額になりました。
もちろん控除額以上の退職金を受け取ろうとすると、所得税がかかってしまうのでオススメができません。それなら退職以前から役員報酬として受け取っておいた方がいいでしょう。
このように退職金を受け取る際にも税法上のメリットがあり、一人親方で個人事業主として働くよりかなり有利に退職金を作れるのです。
控除額を基準に保険を契約する
法人で退職金の積み立て額を考える時、基準にするのは退職金控除です。
退職金控除以上では所得税がかかってしまうので、メリットはありません。その前に給料や役員報酬として受け取っておいた方が無難です。
退職金控除はいつ退職するかを決めておけば、必然と計算ができ、生命保険の返戻金も同時に計算が可能。(代理店の担当に聞けば試算表を出してくれるでしょう)
これをもとに退職する年齢での退職金控除と、返戻金がだいたい同じになるようにして保険を契約しておけば、退職時は現金に困ることなくスムーズに希望の退職金を受け取れるのです。
そもそも退職金はなんのためにあるのか
退職金にはしっかりとした意義が存在します。退職時に支払われるお金は税制上有利だからです。
ただ基本的には国が定年を決めてその老後も生活を補償するために、年金以外にも財源が必要で作ったのが、退職金だったのではないでしょうか。
ですから老後の生活ができれば問題ないわけです。
会社員の退職金であれば、退職金は毎月の給料より税率がかなり優遇されています。ですから会社が勝手に積み立てて退職時に渡すことで、分割で渡すより税金が安くなるのです。
税率は所得税ですので給料などと変わりませんが、退職所得控除が存在し、
- 勤続年数が20年未満の場合は勤続年数×40万円
- 勤続年数が20年以上の場合は、800万円+70万円(勤続年数-20)
の金額が控除されます。その分の金額は非課税になりますので、勤続年数が長ければ長いほど、退職金は優遇されることになっています。
このように退職金は税金を抑えて、会社から大量の収入をもらえる唯一の機会なのです。
これは経営者でも同じ。
自分の会社であったとしても、自分のお金に変えるには多大な税金を支払う必要があります。しかし退職金だけは多額の収入を作っても税金を抑えられるということです。
勤続30年であれば約2000万円もの節税ができる計算です。
このように退職金はただの退職のお祝いとしてもらえるお金ではなく、所得税を支払わずにもらえるお金であるためそれを利用している制度なのです。
老後に必要な金額について考える
以前、金融庁の調査では、老後は公的年金だけでは2000万円ほど足りないという調査結果が出されて問題になりました。
結局この問題はうやむやにされて、なかったことにされていますが、実際に足りないことは明白です。
老後に必要な金額はどのくらいでしょうか?
個人の状況によって変わりますので、明確にはわかりません。
金融庁のいう2000万円もあくまでも平均値を出して試算しただけ。
国民全員は2000万円が必要だとは限りません。むしろもっと足りない人と老後にまったく困らない人が二極化しているのが現状です。
必要な金額は
- 住んでる地域
- 持ち家
- 家族の人数やサポート
- 毎月の生活費
- いつ引退するか
などから、老後に必要な金額を概算で計算することになります。
公的年金は国民年金のみ
次に公的年金での確実に入ってくる収入を計算します。
一人親方にとっては、老後の問題は厚生年金がないこと。
年金は国民年金だけになります。
国民年金が支払われなくなることはありませんが、毎月もらえる年金は満額で7万円程度。
もし持ち家があったとしてもたったの7万円では生活を続けるのは不可能です。
ただしiDeCoという個人年金が用意されていて、この掛け金はすべて経費から賄えて非課税です。
うまく利用すれば2000万円以上の退職金を積み立てることも可能。
掛け金をあげればもっと多くの退職金を積み上げることができます。
しかも一般的な投資と違って、超ローリスクで国民年金と組み合わせればかなりの額の退職金を積み立てられます。
一人親方の年金問題と個人年金については「一人親方は厚生年金に入れない 老後はどうなるのか?」で詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。
国民年金とiDeCoでたりない部分を退職金で
国民年金とiDeCo、そして毎月の生活費を計算した上で、どうしても足りない部分を埋める一つの方法が退職金です。
その金額に合わせて足りない金額を、退職金などで積み立てておく必要があります。
国民年金は必ず加入しておきましょう
国民年金は受給ができると断言できます。
なぜ断言できるのか。国民年金の支払いは自由だからです。
厚生年金はサラリーマンの給料から天引きされるため、強制的に支払われます。
国民年金の加入は法律で義務づけられていますが、支払いするかどうかは個人の自由です。
そして国民年金は支払えば将来確実に得をする構造になっています。
でなければ支払う人がいなくなり、国民年金の制度が成り立たなくなるからです。
現時点で国民年金の総受給額の平均は、総支払い保険料の平均の1.9倍。元本の約2倍の年金を受け取れています。
もちろん将来的に保険料が上がり、受給額が下がる未来は用意に予想できます。
ただし運用利益が出なければ支払う人はいなくなるでしょう。
この現実を考えれば、国民年金を支払う人が得をする仕組みは絶対に崩れません。
あるとすれば日本国が破綻する時です。
ちなみに年金制度が崩れた国はありません。それがプエルトリコのように破綻した国であってもです。
少子高齢化も関係なく、絶対に得をする仕組みでなければ国民年金は成り立たない。
このように国民年金は日本国家が保証する確実に勝てる投資です。
一人親方の退職金の作り方は1つではない
会社員をしていれば、退職金は会社が勝手に用意をしてくれますが、一人親方をしていると自分で準備しておかなければいけません。
税法上のメリットを利用して、可能な限り税金を支払わないように、積み立てていくのがポイントです。具体的には
- iDeCo
- 小規模企業共済
- 建築業界退職金共済制度
- 法人化
などの方法があります。
優先すべきなのは、小規模企業共済でそれでも足りない場合は建退共制度。
会社に利益が出ていて、もっと税金を抑えて退職金を積み立てたい場合は、法人化がオススメです。
まとめ
老後の蓄えとして、ただ貯金するのは税金を支払わないといけませんので、かなり損をしてしまいます。
ですのでしっかりと知識をつけて自分のお金を守り、ちゃんと合法的に退職金を蓄えましょう。
国は準備をしてくれているので、どう利用するかは自分次第です。そういったところにも責任を持つのが個人事業主ですから。
投稿者プロフィール

-
【団体概要と運営方針】中部労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・岐阜労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【中部労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、中部労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
★一人親方部会グループ公式アプ→https://www.saitama631.com/app.html
★一人親方部会クラブオフ→https://www.saitama631.com/cluboff.html
■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』https://www.youtube.com/channel/UCZTlxZRxDDgren56lAn5boQ
最新の投稿
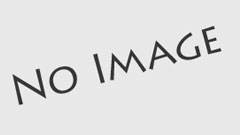 一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について
一人親方豆知識2023年8月10日一人親方の安全衛生教育(災害防止)について よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと
よくある質問2023年5月10日一人親方になるために必ずやるべきこと 未分類2022年7月14日
未分類2022年7月14日 一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること
一人親方豆知識2022年2月18日大工工事の一人親方さんが年収を上げるためにできること